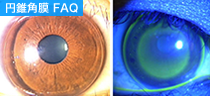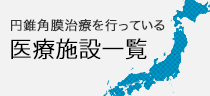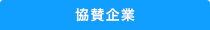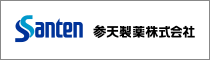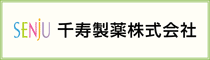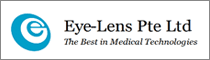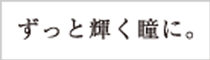お知らせ
第3回円錐角膜研究会 報告 東京医大眼科 森 秀樹
第円錐角膜に対するハードレンズ(HCL)処方―初心者から達人まで使える技法―
円錐角膜に対するHCL処方は、円錐角膜が高度になればなるほど難しく煩わしいが、東京医大式3ステップ法を使えば、初心者でも効率的に最適なレンズを見つけることができる。ただ、検査装置としてCASIAが必要で、円錐角膜用レンズのトライアルを十分に持っていなくてはならない。(スライド1)
最適なレンズを見つけるためには、円錐角膜用レンズをいかに比較するかがポイントになる。私たちは光学部が球面カーブのレンズを好んで用いており、BCを一定にして周辺部デザインが多段階カーブや非球面カーブのものなどをしっかり比較するようにしている。(スライド2)
それではBCはどう決めるのか?重症度に合わせて第一選択のBCを決めておく方法が一般的だが、各施設が独自の基準で行っているのが現状である。
私たちはCASIAで測定したエレベーションマップのBFS値を利用している。(スライド3)
第一選択のBCが決まればあとは、東京医大式3Step法に従って進めていく。Step2では各種円錐角膜用レンズを比較する。やみくもに比較するのではなく重症度によって選ばれる最終レンズには傾向があることを知っておく。軽度や中等度では球面レンズが選択されることが多く、強度の円錐角膜では、円錐角膜用レンズが真価を発揮する。(スライド4)
私たちは円錐角膜用レンズとしてサンコンタクトレンズ社のMカーブとレインボーオプチカル社のタイプBを好んで使用している。工夫していただきたいはその揃え方である。私たちはサイズや周辺デザインを比較しやすいように揃えているが、特に周辺デザインはエッジリフトが高いものと低いものが比較できるように揃えている。BCによってエッジリフトの揃え方を変えているのが
ポイントである。 (スライド5)
レインボーオプチカル社のタイプBトライアルレンズは、ほとんどが特注である。使用してみたい方は「東京医大仕様」希望とメーカーに連絡すると格安で作ってくれるはずである。是非使っていただきたい。(スライド6)
最後のStep3は、涙液交換と視力を考慮してBCを調整する。それでもよいレンズが選べない時はカスタムメイドレンズを考慮するが、カスタムレンズのパラメーターを自分で決めたい人のためにカスタムメイド評価アプリを開発している。乞うご期待。(スライド7.8.9)